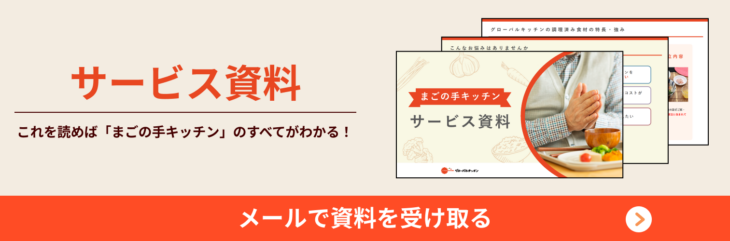12月の行事食一覧|クリスマスや冬至に食べる物の意味も解説

12月は、一年で最も昼の時間が短くなる冬至や、西洋文化に由来するクリスマス、そして一年の締めくくりである大晦日など、様々な行事が行われます。それに伴い、12月の行事食はバリエーション豊かで、それぞれに無病息災や長寿といった願いが込められています。
この記事では、冬至のかぼちゃからクリスマスのチキン、大晦日の年越しそばまで、代表的な12月の行事食とその意味や由来について解説します。
行事食とは?季節の節目に感謝を込めていただく料理
行事食とは、日本の豊かな四季の移り変わりや、お正月、節句といった年間行事に合わせていただく特別な食事を指します。
それぞれの料理には、自然の恵みへの感謝や家族の健康、長寿を願う意味が込められています。
旬の食材を取り入れることで季節の訪れを感じさせ、日々の暮らしに彩りと潤いをもたらす、古くから日本に伝わる大切な食文化といえます。
冬至(12月22日頃)の行事食|無病息災を願って食べるもの
一年で最も夜が長くなる12月下旬の冬至には、無病息災を願って栄養価の高いものを食べる風習があります。
この日を境に再び日が長くなることから、古くは運気が上昇する日とも考えられていました。
厳しい冬を元気に乗り越えるための知恵が詰まった冬至の行事食には、かぼちゃや「ん」のつく食べ物など、縁起の良いとされるものが多くあります。
栄養満点!風邪予防に食べたい「かぼちゃ」

冬至にかぼちゃを食べる風習は、野菜が少なくなる冬場に、栄養豊富な緑黄色野菜を食べて健康に過ごそうという先人の知恵から生まれました。
夏に収穫されるかぼちゃは長期保存がきくため、冬の貴重な栄養源とされてきたのです。
かぼちゃに豊富に含まれるβ-カロテンは、体内でビタミンAに変わり、粘膜を丈夫にして免疫力を高める働きが期待できます。
風邪の予防にも適した食べ物であり、高齢者向けには、やわらかく煮込んだ煮物や、のどごしの良いポタージュスープなどにすると食べやすくなります。
運気を呼び込む「ん」がつく7つの食べ物(冬至の七種)
冬至には、名前に「ん」が2つ付く食べ物を食べると運気が上がるといわれています。
これらは「冬至の七種(ななくさ)」と呼ばれ、なんきん(かぼちゃ)、れんこん、にんじん、ぎんなん、きんかん、かんてん、うんどん(うどん)の7つです。
「ん」がつく食べ物で「運」を呼び込む「運盛り」という縁起担ぎであり、寒い冬を乗り越えるための栄養補給という目的も持ち合わせています。これらの食材を煮物や炊き込みご飯、汁物などに数種類取り入れるだけで、手軽に季節感のある献立を作れます。
邪気を払うとされる縁起の良い「小豆粥」
冬至の行事食として、小豆粥を食べる風習もあります。
古くから小豆の赤い色には邪気を払う力があると信じられており、冬至の日に食べることで翌年一年間の無病息災を願いました。
小豆にはビタミンB群や食物繊維、ポリフェノールといった栄養素が豊富に含まれています。
温かいおかゆは体を内側から温め、消化にも優しいため、食欲が落ちがちな高齢者の方にも食べやすい一品です。
ほんのりとした甘みとやさしい口当たりで、寒い朝の食事に適しています。
クリスマス(12月25日)の行事食|食卓を彩るパーティーメニュー

12月の代表的なイベントであるクリスマスは、特別な食事を楽しむ日として日本でも定着しています。
高齢者施設でも、クリスマスらしい華やかなメニューを提供することで、利用者の方々に季節の訪れを感じてもらえます。
チキン料理やクリスマスケーキといった定番のパーティーメニューを取り入れ、いつもとは違う非日常感を演出することが、利用者に喜んでもらうためのポイントです。
パーティーの主役になる定番の「チキン料理」
クリスマスにチキンを食べる習慣は、欧米で食べられる七面鳥の代わりとして日本で広まったといわれています。
今ではすっかりパーティーの主役として定着し、ローストチキンやフライドチキンなど、様々な調理法で楽しまれています。
高齢者施設での食事として提供する際は、骨付き肉よりも骨なしのもも肉やむね肉を選ぶと安全です。
食べやすい大きさにカットした鶏肉を照り焼きにしたり、クリームソースでやわらかく煮込んだりするなど、調理法を工夫することで、見た目も華やかで食べやすい一品になります。
食後のデザートに欠かせない「クリスマスケーキ」
クリスマスのお祝いに欠かせないのが、華やかに飾られたクリスマスケーキ。日本では、白い生クリームと赤いイチゴを使ったショートケーキが定番で、クリスマスカラーを思わせる見た目も魅力のひとつです。
高齢者施設では、切り分けの手間がなく、個別に提供しやすいカップケーキやロールケーキが便利です。一人分ずつ対応できるため、衛生面でも安心して提供できます。
さらに、咀嚼や嚥下が難しい方にも楽しんでいただけるよう、ムースやババロアなどのやわらかいデザートを取り入れるのもおすすめです。フルーツやアラザンで彩りを添えれば、見た目にも楽しく、食後のひとときがより特別な時間になります。
ドイツの伝統的なクリスマス菓子「シュトーレン」

シュトーレンはドイツ発祥の伝統的なクリスマス菓子で、日本でも近年、パン屋や洋菓子店でよく見かけるようになりました。洋酒に漬け込んだドライフルーツやナッツを練り込んだ生地を焼き上げ、表面にはたっぷりの粉砂糖をまぶすのが特徴です。
本場ドイツでは、クリスマスを待つ「アドベント」の期間に、毎日少しずつスライスして味わう習慣があります。日が経つにつれてフルーツの風味が生地に馴染み、しっとりとした奥深い味わいになるのも魅力のひとつです。
高齢者施設では、定番のケーキとは一味違うデザートとして提供することで、季節感や異文化への興味を引き出すきっかけになります。小さめにカットして個別に提供すれば、食べやすく、会話の種にもなるでしょう。
大晦日(12月31日)の行事食|一年の締めくくりに食べるもの
一年を締めくくる大晦日には、行く年に感謝し、新しい年を無事に迎えられるように願う特別な行事食を食べる風習があります。
代表的なものに年越しそばがありますが、地域や家庭によっては、おせち料理の一部を大晦日から食べ始めたり、家族で鍋を囲んだりすることもあります。
それぞれの食事に込められた意味を知ることで、より深く日本の文化を感じられます。
長寿を願って食べる縁起物の「年越しそば」

大晦日に年越しそばを食べる習慣には、いくつかの意味が込められています。
最もよく知られているのは、そばが細く長いことから「健康長寿」や「家運が長く続くように」と願うものです。
また、そばは切れやすい性質を持つため「一年の苦労や災厄を断ち切る」という意味や、昔の金銀細工師が散らばった金粉を集めるのにそば粉を使ったことから「金運上昇」を願う説もあります。
高齢者向けに提供する際は、すすりやすいように短めに茹でたり、やわらかい鶏肉や刻みネギなど消化しやすい具材を添えたりする工夫が考えられます。
新年を迎える準備として食べる「おせち料理」の一部
おせち料理は、本来新年である1月1日に食べるものですが、地域や家庭によっては大晦日の夜から一部を食べ始めることがあります。
これは「祝い肴」だけでも先にいただくことで、年越しの膳を豪華にするという意味合いがあります。
例えば、「まめに暮らせるように」と願う黒豆や、「子孫繁栄」を願う数の子などを少しずつつまみながら、新年を迎える準備をします。
一足早くお正月気分を味わうことができ、利用者の方々の会話も弾むきっかけとなる食事です。
年末の団らんを彩る「すき焼き」や「カニ鍋」

大晦日の夜に、鍋を囲むのも日本の年末らしい光景です。
普段より少し贅沢なすき焼きや、旬の味覚であるカニ鍋は、一年の締めくくりにふさわしいごちそうとして人気があります。
一つの鍋をみんなで囲む食事のスタイルは、自然と会話が生まれ、和やかな雰囲気を作り出します。
高齢者施設でも、やわらかく煮込んだ牛肉や野菜、豆腐などを中心としたすき焼き風の煮物や、ほぐしたカニの身を入れたお鍋を提供することで、手軽にごちそう気分を味わってもらえます。食べやすさに配慮しながらも、季節感と特別感を演出できるメニューとしておすすめです。
まとめ
12月は冬至、クリスマス、大晦日と、一年の締めくくりにふさわしい行事が続きます。かぼちゃや年越しそばなど、季節の食材や伝統料理にはそれぞれ意味や由来があり、利用者の方との会話のきっかけにもなります。行事食は、日々の食卓に彩りを添え、献立のマンネリ化を防ぐ大切な役割も果たします。
冬至を過ぎれば新年、そしてひな祭りへと、季節の行事は絶え間なく続いていきます。すべてを手作りで準備するとなると、献立作成から調理・盛り付けまで、現場スタッフにとって大きな負担になることもあります。だからこそ、無理なく継続できる仕組みづくりが欠かせません。
そんな時に頼れるのが、外部の食事提供サービスです。なかでも「まごの手キッチン」は、咀嚼・嚥下に配慮した介護食に加え、季節や行事に合わせた特別メニューも豊富に取り揃えています。調理済みの冷凍食材を湯煎や解凍するだけで提供できるため、現場の負担を大幅に軽減しながら、利用者の方に“特別なひととき”を届けることができます。
現在「まごの手キッチン」では、高齢者施設様向けに無料試食サンプルを提供中です。まずは実際に味や使い勝手を試してみることで、導入後のイメージが具体的になります。利用者様には、毎日のお食事とはひと味違う行事食の楽しみを。スタッフの皆様には、無理なく質の高い食事を届けられる安心を。そんな両方を叶える選択肢として、ぜひご活用ください。