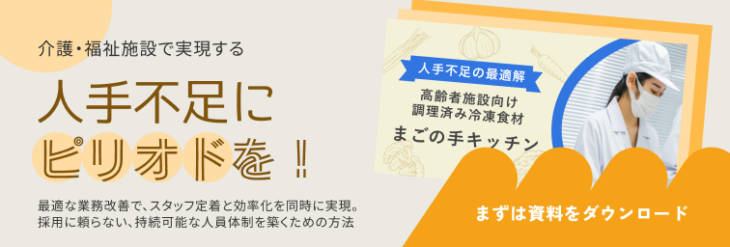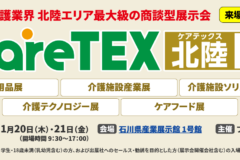介護施設の人材不足を解決する方法とは?人材不足の現状や原因を解説
 介護業界は深刻な人材不足に陥っており、介護施設での介護の質や利用者満足度の低下が懸念されています。このまま人材不足が進行すると、介護サービスの持続性も危ぶまれる状態です。
介護業界は深刻な人材不足に陥っており、介護施設での介護の質や利用者満足度の低下が懸念されています。このまま人材不足が進行すると、介護サービスの持続性も危ぶまれる状態です。
実際に介護現場の方のなかにも、「なぜこれほど人材不足が深刻なの?」「人材不足の解決策は?」と疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、介護業界の人材不足の現状や背景、原因について解説します。介護施設の人材不足を解決する方法や人材を増やす方法も紹介するので、人材不足にお悩みの介護施設の方はぜひ参考にしてみてください。
介護業界の人材不足の現状
介護業界では慢性的な人材不足が続いており、その深刻さは年々増しています。厚生労働省の調査によると、2025年には約245万人、2040年には280万人の介護職員が必要とされている(参考:第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について、 厚生労働省)一方で、すでに十分な人材を確保できていない施設が多く存在するのが現状です。
とくに特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、常に利用者の生活全般を支える必要がある介護施設では、慢性的な人員不足が介護の質や利用者満足度の低下につながるおそれもあります。
このような状況の中で、人材不足が業務負担の増大や離職率の上昇といった悪循環を引き起こし、介護サービスそのものの持続性が問われる段階に達しています。
介護業界の人材不足の背景
介護業界の人材不足の背景には、高齢化と少子化があります。それぞれの影響についてチェックしておきましょう。
高齢化
日本は世界でも類を見ない速度で高齢化が進んでおり、社会全体にさまざまな影響を及ぼしています。総務省の発表によると、2024年9月時点で65歳以上の高齢者人口は約3,625万人に達し、総人口に占める割合は29.3%となりました(参考:統計からみた我が国の高齢者、総務省)。これは世界最高水準であり、日本が「超高齢社会」であることを象徴しています。
高齢者の増加に伴い、介護を必要とする人も年々増加しています。厚生労働省の推計によれば、要介護(要支援)認定者数は2023年3月末時点で694万人です(参考:令和4年度 介護保険事業状況報告、厚生労働省)。2025年には団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」が本格化することで、介護ニーズはさらに高まると予想されています。
加えて、要介護者の高齢化も進行しており、90歳以上の高齢者も急増しています。これにより、介護サービスにはより専門性と多様な対応力が求められるようになっており、現場の負担は増加傾向です。
このように、介護需要は今後も右肩上がりで推移することが見込まれている一方で、それを支える人材の確保が追いついていません。高齢化は単なる利用者の増加だけでなく、介護従事者の高齢化という二重の課題をも内包しており、制度面・人材面の両面からの対応が急務とされています。
少子化
日本の少子化も深刻な社会課題であり、介護業界の人材不足に直接的な影響を及ぼしています。2024年の厚生労働省の統計によると、出生数は過去最少の68万人台となり、年々減少傾向です(参考:令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況、厚生労働省)。これにより、生産年齢人口(15〜64歳)の減少が加速し、労働力の確保が困難になっています。
とくに介護業界は、若年層や中堅層を中心とした担い手を必要としていますが、少子化によってその母数自体が年々縮小しているため、人材の取り合いが激化傾向です。他業種と比較して待遇や労働条件が厳しいとされる介護職は、若年層の間で選ばれにくい傾向があり、慢性的な人材難に陥っています。
また、大学進学率の上昇や都市部への人口流出も相まって、地方の介護施設ではさらに人材確保が難しくなっています。若者が都市部での就職を希望する中で、地方では高齢化が進み、需要と供給のバランスが大きく崩れているのが現状です。
さらに、少子化は単に労働人口の減少にとどまらず、「家族による介護力」の低下も引き起こす原因です。かつては三世代同居によって家族内で支えられていた高齢者の生活も、核家族化や未婚率の上昇により困難となり、介護サービスの依存度が増しています。
このように、少子化は介護業界の人手不足を複合的に悪化させる要因であり、将来的には外国人材のさらなる受け入れや、テクノロジー活用による労働生産性の向上が求められる状況です。
介護業界の人材不足の原因
介護業界の人材不足の主な原因としては、以下の4つが挙げられます。
- 仕事内容に対して賃金が低い
- 人間関係で悩みやすい
- 介護業務は身体へ負担がかかる
- 業務効率が悪い
それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。
仕事内容に対して賃金が低い
介護職は利用者の生活全般を支える非常に重要な職種でありながら、その賃金水準は他産業と比べて相対的に低く設定されています。厚生労働省の統計では、介護職員の平均月収は全産業平均を大きく下回っており、「生活が苦しい」と感じる職員も少なくありません。
仕事内容には身体的・精神的な負荷が多く含まれるにもかかわらず、それに見合う報酬が得られない現状が、人材確保や離職率の高さにつながっていると考えられます。とくに若年層や子育て世代にとっては、収入の安定性や昇給の見通しが重視されるため、介護職が選ばれにくくなる傾向にあるといえるでしょう。
人間関係で悩みやすい
介護現場では、チームでの協力が欠かせないため、日々の業務において多職種との連携や情報共有が頻繁に行われます。これは介護の質を高めるうえで非常に重要な要素である一方で、立場や役割の違いによって意思疎通に工夫が必要な場面もあるでしょう。
利用者やその家族とのコミュニケーションに加え、同僚・看護師・ケアマネジャー・管理者など、さまざまな関係者との関わりが求められるため、人間関係のバランス感覚や調整力が問われる場面も少なくありません。
また、新人職員や異業種から転職してきた人にとっては、業界特有のコミュニケーションの文化やルールに戸惑うこともあります。そのため、スムーズに職場に適応するためのサポート体制が整っているかどうかが、働きやすさを左右する重要なポイントとなります。
介護業務は身体へ負担がかかる
介護業務では、利用者の身体介助、入浴や排泄の補助、ベッドからの移乗といった身体的な負担が大きい作業が日常的に発生します。これらの作業は長時間にわたることも多く、腰痛や関節の痛みに悩まされる職員も少なくありません。
さらに、夜勤やシフト勤務がある施設では生活リズムが不規則になり、健康への影響も懸念されます。こうした身体的負担の大きさが、とくに中高年層の介護職員にとっては離職を選ぶ一因となることもあるでしょう。
業務効率が悪い
介護現場では、記録業務や申し送り、報告書作成などの煩雑な事務作業が、職員の負担を大きくする原因となっています。紙ベースの管理や非効率な情報共有の仕組みが残っている施設も多く、本来の介護業務に集中できないケースもあるでしょう。
また、業務の標準化がされていない現場では、ベテラン職員と新人職員との間で作業の進め方に差があり、無駄な時間や労力が発生しています。このような非効率な運用は、業務過多による離職や人材定着率の低下の原因のひとつです。
介護施設の人材を増やす方法
介護施設の人材を増やす方法として、以下の3つの方法を紹介します。
- 待遇を改善する
- 介護職のイメージアップに取り組む
- 多様な人材を確保・育成する
それぞれ詳しくチェックして、自施設の取り組みに活かしてみてください。
待遇を改善する
人材確保の最優先課題として、多くの介護施設が取り組むべきは待遇改善です。これは単に給与を上げるだけにとどまらず、働く環境そのものを総合的に見直すことを意味します。たとえば、基本給の引き上げに加え、夜勤手当や資格手当、住宅手当など各種手当の充実、賞与支給の安定化などが必要です。
また、退職金制度の導入や、子育て支援制度の整備、柔軟な勤務体系(時短勤務や選択シフト制など)の導入も、ワークライフバランスを重視する人材にとっては魅力的です。定期的な昇給制度やキャリアアップを目指せる職能評価制度を導入することで、長期的な定着にもつながります。
介護職のイメージアップに取り組む
介護職に対して「きつい・汚い・危険(3K)」というネガティブな印象を持つ人も少なくありません。しかし実際には、人とのふれあいや社会貢献の実感が得られる、非常に価値ある仕事です。こうした本質的な魅力を広く社会に発信していくことも、人材確保につながる可能性があります。
たとえば、SNSや動画サイト、地域メディアを活用した現場紹介コンテンツの配信、現役介護士によるインタビュー記事や体験談の共有、施設見学ツアーや職場体験イベントの開催などが効果的です。とくに若年層に対しては、介護職に就くことで得られるキャリアパスやスキル習得の機会を具体的に示すことで、将来の選択肢としての可能性を提示できるでしょう。
また、学校や専門機関と連携し、授業や講演を通じて介護現場の実態ややりがいを伝えることも、長期的な人材育成に有効です。介護職の社会的価値を広めることで、業界全体の人材確保力が高まります。
多様な人材を確保・育成する
介護現場の人材不足に対応するには、これまで十分に活用されてこなかった多様な人材に着目し、その受け入れ体制を整えることが求められます。
具体的には、以下のような層が対象となるでしょう。
- 外国人介護人材:特定技能やEPA、技能実習制度などを活用し、日本語教育と並行して介護技術の研修を行うことで戦力化が可能
- シニア人材:定年退職後の元介護職や異業種出身の高齢者が、自身の経験や知識を生かして働ける場を提供することで、貴重な労働力になる
- 主婦層・子育て世代:短時間勤務や託児所完備、急な休みに対応できる柔軟なシフト体制などを導入すれば、潜在的な人材が活躍できる環境になる
- 未経験者・異業種からの転職者:研修制度やOJT、メンター制度の充実により、無資格・未経験者でも安心して介護職にチャレンジできるようになる
このように、受け入れ側の制度整備と育成体制が充実すれば、人材の裾野は大きく広がり、業界全体の持続可能性にも貢献します。
介護施設の人材不足の解決策
介護施設の人材不足の主な解決策としては、以下の3つが挙げられます。
- 不安や悩みなどを相談できる場を設ける
- ITツールやシステムを導入する
- 調理済み食材提供サービスを利用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
不安や悩みなどを相談できる場を設ける
介護職員が安心して長く働き続けるためには、心理的なケアとコミュニケーション環境の整備が不可欠です。日々の業務の中で生じるストレスや悩みを一人で抱え込むことなく、気軽に相談できる体制を整えることが、職員の離職防止に大きく寄与します。
具体的には、以下のようなものの導入が効果的です。
- 定期的な個別面談の実施
- 匿名で意見を投稿できる意見箱やアンケート
- メンタルヘルス研修の導入
- 社内相談員の配置
- 外部のカウンセラーと連携したサポート体制の構築
また、チームビルディング研修やレクリエーションの開催、表彰制度などを通じて職員同士の信頼関係を深める取り組みも重要です。心理的安全性が確保された職場では、職員が主体的に動き、離職リスクの大幅な減少が期待できます。
ITツールやシステムを導入する
介護現場の業務効率化は、限られた人員でも質の高いサービスを提供し続けるためのポイントとなります。そのためには、ICTやIoTの積極的な導入が不可欠です。
たとえば、介護記録を電子化することで、手書き作業の削減と情報の一元化が可能になり、報告・申し送り業務のミスも軽減されます。また、シフト管理システムや勤怠管理ツールを導入すれば、業務計画の最適化や勤務状況の可視化も実現可能です。
さらに、利用者の転倒リスクやバイタルを常時監視する見守りセンサー、ベッドからの起き上がりを検知するマットセンサー、自動排泄処理装置や移乗支援ロボットなどの導入により、身体的な負担の大幅な軽減も期待できます。
こうしたテクノロジーの活用は、介護の質を落とさずに業務量を抑える手段として、今後の介護施設運営において重要な位置を占めるでしょう。
調理済み食材提供サービスを利用する
介護施設における業務の中で、食事提供は大きなウェイトを占めています。朝・昼・夕すべての食事を用意するためには、栄養バランスや衛生管理にも細心の注意が必要です。調理スタッフや介護職員の負担は大きくなります。
このような負担を軽減する手段として注目されているのが、調理済み食材提供サービスの活用です。これらのサービスでは、管理栄養士が監修したメニューがすでに調理された状態で届けられるため、現場では湯煎や盛り付けのみで済み、調理時間を大幅に短縮できます。
また、食材の発注・在庫管理・衛生管理といった業務も簡素化され、トータルでの作業効率が飛躍的に向上します。さらに、食事の質が安定することで、利用者の満足度向上にもつながります。人手不足に悩む施設にとって、外部リソースの有効活用は、職員の業務負荷を減らし、コア業務に集中するための有力な選択肢となるでしょう。
まとめ
本記事では、介護業界における人材不足の現状や背景、その原因などについて解説しました。進行する高齢化と少子化により、介護を必要とする高齢者が増える一方、介護する労働人口は減少しています。賃金の低さや負担の大きさから、働き手が集まらないのも大きな課題です。
介護施設の人材不足を解決するためには、待遇の改善や介護業界自体のイメージアップ、多様な人材の雇用などが求められます。また、ITツールや調理済み食材提供サービスなどを導入し、業務効率を高めることも大切です。
介護施設向けの食事サービスなら、グローバルキッチンの「まごの手キッチン」がおすすめです。「まごの手キッチン」は、高齢者の方向けの調理済み冷凍食材をお届けする食材提供サービスです。リーズナブルで高齢者にやさしい食事を豊富に揃え、管理栄養士による毎月の献立も提供します。栄養価調整食ややわらか食、ムース食にも柔軟に対応可能です。
「まごの手キッチン」の導入により、食事の用意にかかる人件費や水道光熱費など大幅なコスト削減を実現し、手間なく安全な食事を提供できるようになります。これまで調理に割いていた人材を、より中核業務に回すことで人材不足への対策も可能です。
「まごの手キッチン」では、高齢者施設で提供する食事や介護食を検討している法人向けに、無料試食サンプルを提供しています。
ぜひこの機会に、お気軽にお問い合わせください。