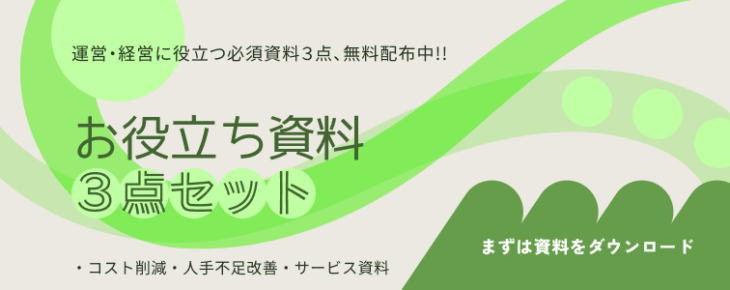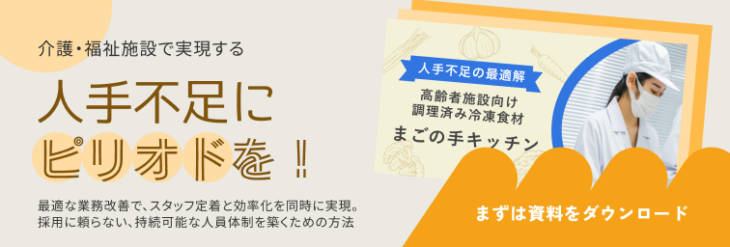介護施設経営を成功させる方法とは?現状や課題について解説
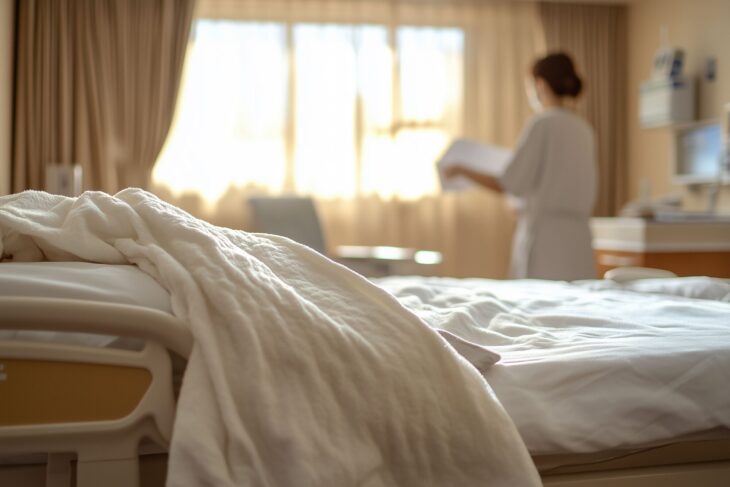
介護施設経営は、高齢化が急速に進む日本において必要とされている事業のひとつです。2040年には、国民の約35%が65歳以上になると予想されており、その対応のために介護施設経営にも注目が集まっています。
一方、介護施設経営は国の政策からの影響を受けやすい点や人手不足などの課題も抱えているため、「介護施設経営の成功のポイントを知りたい」「介護施設経営の課題やメリットを整理したい」といった方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、介護施設経営の現状やメリット、抱えている課題などを解説します。どうすれば介護施設経営がうまくいくのか、成功のためのポイントも紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。
介護施設経営の現状
日本社会は急速に高齢化が進行しており、介護サービスに対する需要は年々高まっています。内閣府の発表によると、2035年には国民の約3人に1人が65歳以上になるとされ、要介護者数も今後さらに増加していく見込みです。これに伴い、介護施設の新設や経営に注目が集まっています。
介護施設には、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、さまざまな形態が存在しています。それぞれに対象者やサービス内容、収益モデルが異なり、運営法人の種類(医療法人、社会福祉法人、民間企業など)によっても特徴があります。
<介護施設の種類>
|
種類 |
対象者 |
主なサービス |
|
特別養護老人ホーム(特養) |
要介護3以上の高齢者 |
介護・生活支援・健康管理 |
|
介護老人保健施設(老健) |
要介護1以上の高齢者 |
リハビリ・介護・医療ケア |
|
有料老人ホーム |
自立~要介護 |
介護・生活支援・食事提供 |
|
グループホーム |
認知症の診断を受けた要支援2以上の高齢者 |
共同生活・認知症ケア・介護 |
|
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
比較的自立した高齢者 |
見守り・生活相談・安否確認 |
民間企業による参入も進んでおり、競争が激化する一方で、介護報酬制度や人員配置基準といった国の政策に強く依存するため、制度改正の影響を受けやすいビジネスであることも特徴です。とくに介護報酬の見直しが2〜3年ごとに行われることから、中長期的な事業計画を立てる際には、制度動向を的確に把握しておく必要があります。
さらに、新型コロナウイルスの影響により、施設内の感染症対策や衛生管理が経営上の重要課題として浮上しました。感染症対策に伴うコスト増加や、面会制限による利用者家族の不満対応、入居率の低下なども経営に影響を与えており、柔軟かつ迅速な対応力が求められています。
介護施設経営のメリット
介護施設経営のメリットは、主に以下の3点です。
- 長期的な収益が見込める
- 将来的な需要が期待できる
- 土地活用ができる
それぞれのメリットについてチェックしてみましょう。
長期的な収益が見込める
介護施設は、一度入居者が決まれば長期間にわたって継続的な収入を得られるビジネスモデルです。ほかのサービス業やテナントビジネスに比べて、収益の安定性が非常に高いと言われています。入居者が契約後すぐに退去することは少なく、一般的には2〜3年以上、特養などでは5年以上の長期入居も珍しくありません。
また、入居者の介護度が高くなるにつれて施設の提供するサービスが増加し、それに応じて介護報酬も加算される仕組みがあります。加えて、介護報酬の一部は公費によって賄われるため、景気変動に左右されにくく、経済の不安定期でも比較的収入が落ち込みにくいのもメリットです。
さらに、継続的に収益が入ることで、長期的な視点での設備投資や人材育成計画が立てやすく、結果として施設の運営基盤をより強固なものにする好循環が生まれます。
将来的な需要が期待できる
日本は超高齢社会に突入しています。65歳以上の人口比率は30%を超え、今後も増加傾向が続くでしょう。2040年には約3,900万人が65歳以上となると推定され、これに伴って介護施設へのニーズも急増することが予想されます。中でも認知症患者数の増加は顕著で、認知症対応が可能な施設への需要は年々高まっています。
また、核家族化や単身世帯の増加により、家庭内での介護が難しくなってきており、「施設に預けたい」「プロのケアを受けさせたい」といった家族のニーズも増加中です。加えて、働きながら親の介護をする「ビジネスケアラー」の負担軽減のためにも、施設ケアの需要は高まっており、将来にわたって安定した市場性がある分野といえます。
さらに政府も在宅と施設を併用した「地域包括ケアシステム」を推進しており、民間の介護施設への支援体制や補助制度も強化されつつあります。このように社会・行政の両面から支えられていることも、将来性の裏付けだといえるでしょう。
土地活用ができる
介護施設は、住宅地や商業地だけでなく、郊外の遊休地や相続で取得した土地などを有効活用する手段のひとつです。土地が広くなくても小規模多機能型施設やグループホームといった小型施設であれば事業化が可能であり、地域ニーズに応じた施設設計によって柔軟な活用が期待できます。
また、土地所有者にとっては不動産価値の維持・向上だけでなく、安定した収入源となる点も大きなメリットです。たとえば、土地を賃貸する方式であれば、オーナーは建物や運営リスクを負うことなく、長期的に安定した賃料収入を得ることができます。一方で、自ら事業主となって施設を運営する場合も、地域貢献性が高く、金融機関からの融資を受けやすい分野であるという利点があります。
さらに、介護施設は社会的インフラとしての役割を持つため、補助金や税制優遇の対象にもなりやすく、資産活用と社会貢献を両立できる点で非常に有望な選択肢といえるでしょう。
介護施設経営の課題
介護施設経営で課題となるポイントは、主に以下の4点です。
- 利益率
- 利用者の確保
- 人材の確保
- 競合施設との差別化
それぞれの課題についてみていきましょう。
利益率
介護施設経営は社会的な意義が大きい一方で、利益率が高くないという構造的な課題を抱えています。介護報酬制度に基づいた運営であるため、自由な価格設定が難しく、提供できるサービスに対して上限が設けられているのがその原因です。結果として、いくらサービスの質を上げても、売上を飛躍的に伸ばすことは困難だといえます。
また、経営の多くを占めるのが人件費であり、施設によっては70%以上が人件費というケースも珍しくありません。さらに近年は最低賃金の引き上げや物価高騰、エネルギーコストの増加など経費の増大要因が多く、経営を圧迫する要素が年々増えています。
このような中で利益を確保するためには、空床を出さない工夫、業務効率化による人件費の抑制、介護加算を活用した報酬最大化など、さまざまな経営努力が求められます。
利用者の確保
かつては介護施設が足りないと言われていた時代がありましたが、今では地域によっては施設数が充足しており、競争が激化しています。とくに都市部では介護施設が乱立しており、単に開設すれば入居者が集まるというわけではありません。
また、利用者側の目も肥えており、価格だけでなくサービス内容や職員の対応、食事の質、建物の設備、医療連携体制、認知症対応可否など、選定基準が非常に多様化しています。家族の立場から見ても、「安心して預けられるかどうか」が施設選びの重要なポイントであり、口コミや見学対応の質が入居決定に影響を与えることも多いでしょう。
そのため、入居者獲得のためには広報戦略の強化、地域包括支援センターやケアマネジャーとの関係構築、医療機関との連携体制の整備など、戦略的な営業活動が必要になります。
人材の確保
介護施設の運営で最も大きな悩みの一つが「人材不足」です。厚生労働省によると、2040年には介護職員が約69万人不足すると試算されており、とくに都市部では人材の取り合いが深刻化しています。応募自体が少ないだけでなく、せっかく採用しても過酷な労働環境や将来性の不安から短期離職につながってしまうことも珍しくありません。
また、有資格者(介護福祉士・看護師・社会福祉士など)の確保が難しい状況が続いており、現場は常にギリギリの人員で運営せざるを得ない状態に陥っている施設もあります。
人材確保のためには給与の引き上げだけでなく、福利厚生の充実、研修制度の整備、外国人材の受け入れ、キャリアアップ支援、現場での精神的サポートなど、多面的なアプローチが求められています。
競合施設との差別化
今や介護施設は地域に数多く存在しており、入居者は施設を「選べる」時代に入りました。そのため、自施設の存在価値を高め、他の施設と明確に差別化を図ることが経営において不可欠です。
差別化の切り口としては、認知症専門のケア・高度な医療との連携・特定疾患への対応・食事のこだわり・リハビリ重視・レクリエーションの充実度などがあり、自施設の強みを戦略的に打ち出すことが重要です。単に「安心・安全」といった抽象的な訴求ではなく、具体的な特徴や実績を可視化する工夫が求められます。
また、家族が情報を得る際はWebサイトやパンフレット、見学時の対応などが判断材料になるため、情報発信の質と一貫性も競争力に直結します。
介護施設経営を成功させる方法
介護施設経営を成功させるためのポイントとして、以下の3つが挙げられます。
- 労働環境を整える
- IT活用で業務を効率化する
- 近隣の介護施設をリサーチする
各ポイントをチェックして、介護施設経営に活かしてみてください。
労働環境を整える
介護施設の成功において、職員の定着率を高めることは極めて重要です。慢性的な人材不足が業界全体の課題である今、優秀な人材をいかに確保し、長く働き続けてもらうかが、安定経営の鍵を握っています。そのためには、まず労働環境の整備が欠かせません。
具体的には、長時間労働や夜勤過多などの過酷な勤務体制を見直し、適切なシフト体制の構築が必要です。また、有給休暇が取りづらい職場では職員の不満が蓄積されやすいため、休暇取得を促進する取り組みも求められます。
さらに、介護職員の多くは心身の負担を抱えながら勤務しているため、メンタルヘルスケアやストレスチェック制度の導入も有効です。ハラスメントのない職場づくりや、育児・介護との両立支援、時短勤務制度など、ライフスタイルに寄り添った柔軟な勤務体制の整備も重要です。
職場の雰囲気づくりも軽視できません。管理職と現場職員の信頼関係や、チーム内のコミュニケーションの活性化、感謝の言葉を伝える風土などが、働きやすさに直結します。施設経営では、「人が辞めない職場づくり」を経営の最優先課題のひとつとして位置づけるべきでしょう。
IT活用で業務を効率化する
介護業務の現場では、日々のケアだけでなく、記録作成・報告書の作成・職員間の情報共有・家族への連絡など、多くの事務作業が発生します。これらの業務が煩雑で非効率なままでは、職員の負担が増し、サービスの質にも悪影響を及ぼします。そこで、ITの活用による業務効率化が不可欠です。
たとえば、タブレットを用いたリアルタイムの介護記録入力によって、記録の手間とミスを大幅に削減できます。また、クラウド型のシステムを導入することで、他職種との情報共有やケア内容の一元管理が可能となり、チームケアの精度が向上するでしょう。
さらに、勤怠管理やシフト作成の自動化・入退所手続きのペーパーレス化・請求業務の効率化なども、業務時間の短縮と人的ミスの防止に寄与します。近年では、AIやIoTを活用した見守りセンサーやナースコール連携システムなども普及しつつあり、夜間の職員配置削減や事故予防にも効果を発揮しています。
IT導入にかかる初期コストについては、自治体の補助金制度や国のICT導入支援制度などを活用することで軽減可能です。経営効率化だけでなく、職員のストレス軽減やサービスの均質化を図る上でも、ITは介護施設経営における強力な味方となるでしょう。
近隣の介護施設をリサーチする
介護施設を成功に導くには、周囲の市場環境を的確に把握することが欠かせません。自施設が立地する地域において、どのような競合施設が存在し、どのようなサービスを提供しているかを把握しないまま運営を進めると、入居者獲得や職員採用で不利な立場に置かれる可能性が高くなります。
たとえば、周囲にリハビリ特化型の老人ホームが多数存在する場合、自施設が同様の路線で勝負しても差別化が困難です。むしろ認知症対応や看取り支援、医療との連携、アクティビティ重視など、他とは異なる強みを明確に打ち出す必要があります。
地域分析の際は、競合施設の価格帯・入居率・職員体制・Webサイトでの訴求ポイント・口コミ評価・行政の評価結果などもチェックすべき項目です。また、介護支援専門員(ケアマネ)や地域包括支援センター、訪問医や薬剤師といった関係者の声からも、現場のニーズや地域課題を掘り下げることができます。
さらに、地域の高齢化率や将来推計人口、世帯構成の変化、介護保険事業計画なども情報源として有効です。こうした「地域の声」に耳を傾けることで、自施設の運営方針やサービス設計がより現実的かつ的確なものになります。
まとめ
本記事では、介護施設経営の現状やメリット、課題などについて解説しました。介護施設経営は、高齢化が進む日本では将来的な需要や、長期的な収益が期待できる点などがメリットです。一方、利益率を上げにくい点や競合との差別化が難しい点などは、介護施設経営の課題として挙げられます。
介護施設経営を成功させるためには、労働環境の整備や業務の効率化、近隣の介護施設との差別化などが重要です。働きやすく地域で特色のある施設とすることで、スタッフや利用者から選ばれる施設となるでしょう。
介護施設の業務効率やコストの改善を目指すなら、グローバルキッチンの介護施設向けの食事サービス「まごの手キッチン」がおすすめです。「まごの手キッチン」は、高齢者向けの調理済み冷凍食材をお届けする食材提供サービスです。リーズナブルで高齢者にやさしい食事を豊富に揃え、管理栄養士による毎月の献立も提供します。栄養価調整食や常食・やわらか食・ムース食にも柔軟に対応可能です。
「まごの手キッチン」の導入により、食事の用意にかかる人件費や水道光熱費など大幅なコスト削減を実現し、手間なく安全な食事を提供できるようになります。
「まごの手キッチン」では、介護施設を運営している法人向けに無料試食サンプルを提供しております。ぜひこの機会に、お気軽にお問い合わせください。