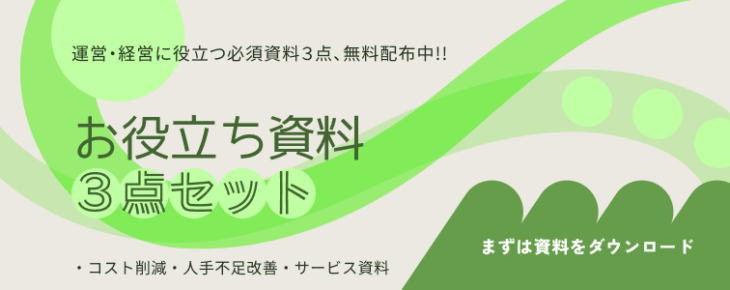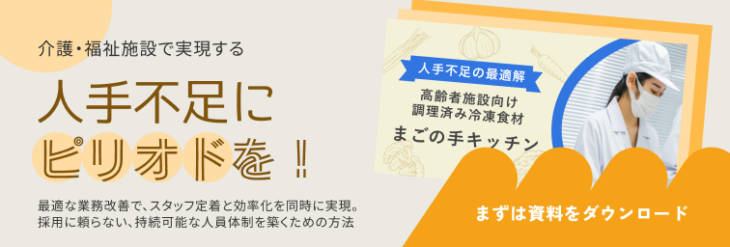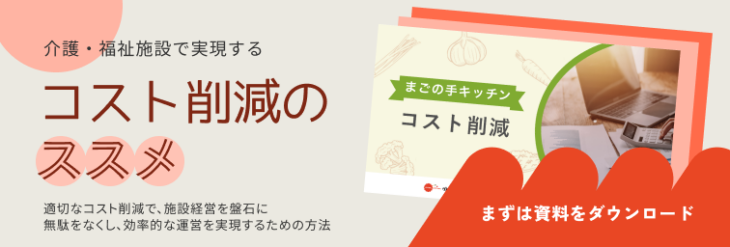デイサービスの経営は厳しい!原因や改善方法を解説

高齢化が急速に進む日本において、デイサービスなどの介護施設の需要は年々高まっています。しかし、デイサービスを含む介護施設の倒産件数は増加傾向であり、その経営の難しさがうかがえます。
本記事では、デイサービスの現状や直近の倒産件数などから、デイサービスの経営の難しさについて解説します。経営を改善するための施策も紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
デイサービスの現状
日本は世界でも有数の超高齢社会に突入しており、デイサービス(通所介護)の重要性は年々高まっています。2023年時点で65歳以上の高齢者人口は約3,623万人と、総人口の約29.1%を占め(参考:統計からみた我が国の高齢者、総務省統計局)、2042年には約3,953万人に達する見通しです(参考:将来推計人口・世帯数、国立社会保障・人口問題研究所)。このような人口構造の変化により、要介護者の数も増加の一途をたどっており、2021年度時点で要介護・要支援認定者は約690万人に上ります(参考:介護保険事業状況報告、厚生労働省)。
このような背景から、デイサービスの利用者数も増加傾向です。デイサービスは、在宅介護を支える重要な役割を担っており、介護負担の軽減、社会参加の促進、身体機能の維持など、さまざまな面で高齢者やその家族を支えています。
一方で、提供側であるデイサービス事業所の数は横ばいからやや減少傾向にあります。特に地域密着型の小規模デイサービスは減少が顕著で、今後の供給体制に懸念が生じています。
需要が高まる中、サービス提供拠点が十分に確保されていない地域もあり、都市部では競争の激化、地方ではサービス不足という二極化が進んでいます。今後さらに進む高齢化に対応するには、事業所の新規開設だけでなく、既存施設の運営安定化や人材の確保、サービスの質の向上など、多方面からの対策が求められています。
デイサービスの倒産件数
近年、デイサービスを含む介護事業全体で倒産件数が増加傾向にあります。とくに新型コロナウイルスの影響を受けた2020年以降、その傾向はより顕著です。
|
年 |
介護事業全体の倒産件数 |
通所・短期入所(デイサービスなど)の倒産件数 |
|
2020年 |
118件 |
38件 |
|
2021年 |
81件 |
17件 |
|
2022年 |
143件 |
69件 |
|
2023年 |
172件 |
56件 |
|
2024年 |
179件 |
55件 |
参考:「老人福祉・介護事業」の倒産状況、東京商工リサーチ
2020年度には、介護事業全体で118件の倒産が発生し、うちデイサービスなどを含む「通所・短期入所介護事業」の倒産件数は38件に上りました。これは、全体の約32%を占めており、業態別でも最も多い水準です。その後、2021年度は一時的に減少したものの、2022年度には再び大幅に増加し、通所介護の倒産件数は69件と、過去最高クラスの水準に達しました。
2023年度以降も倒産件数の高さは続き、2024年度には介護事業全体の倒産件数が179件と過去最多を記録しました。このうち、通所・短期入所事業は55件となっており、引き続き高水準で推移しています。
倒産が多い理由としては、利用者数の伸び悩みや職員不足、物価高騰による経費の増大、地域内での過当競争など、複数の要因が重なっていることが挙げられます。とくに小規模・零細のデイサービス事業所は、売上不振や資金繰りの悪化によって経営継続が困難となりやすく、倒産リスクが高い傾向にあります。
このように、デイサービスの倒産件数は長期的な傾向として増加しつつあり、安定した経営を続けるには、戦略的な運営と早期の経営改善が欠かせない状況です。
デイサービスの経営が厳しい原因
デイサービスの経営が難しい主な原因としては、以下の4つが挙げられます。
- 利益が少なくなっている
- 人材確保・定着が難しい
- 経費が増加している
- 競合が多い
それぞれの原因について詳しくチェックしてみましょう。
利益が少なくなっている
デイサービス事業は、収益の大部分を介護報酬によって得ていますが、その利益率は非常に低く、経営を安定させるには極めて厳しい構造となっています。厚生労働省の「令和4年度 介護事業経営実態調査」によると、通所介護(デイサービス)の収支差率(税引前利益率)はわずか1.0%にとどまっています。つまり、売上高のうち利益として残る割合がほとんどなく、わずかなコスト増でも赤字に転落するリスクが高いことを意味します。
利益が出にくい構造は一過性の問題ではなく、制度的・構造的な課題です。持続可能な運営を実現するためには、コスト管理の徹底、収益モデルの見直しが不可欠です。
人材確保・定着が難しい
介護業界全体に共通する課題として、慢性的な人材不足が挙げられます。デイサービスにおいても例外ではなく、とくに介護職員・看護職員の確保と定着は大きな経営課題です。
介護職は肉体的・精神的な負荷が大きいにもかかわらず、賃金水準が他産業に比べて低いため、離職率が高い傾向にあります。新人職員が定着せず、採用コストがかさみ、既存職員に負荷が集中するといった負のスパイラルが経営に影響を及ぼしているといえるでしょう。
経費が増加している
デイサービスの運営において、経費の増加は経営を圧迫する大きな要因のひとつです。近年では、とくに人件費・光熱費・燃料費・感染症対策費といった支出が増加しています。
人件費については、最低賃金の引き上げが全国的に進んでおり、スタッフの確保や定着を図るうえでの処遇改善も求められるため、コストが年々膨らんでいます。加えて、採用が難しい環境では紹介会社を利用するケースも多く、採用経費も軽視できません。
また、光熱費やガソリン代の上昇は、施設内での空調使用や送迎サービスを提供するデイサービスにとって無視できない負担です。送迎車両の維持管理費や燃料費、保険料も、施設の規模に応じて重くのしかかってきます。
競合が多い
デイサービスはほかの介護サービスに比べて比較的参入障壁が低く、新規参入が相次いだ結果、地域によっては事業所数が飽和状態に近づいています。とくに都市部では、1つのエリア内に複数の事業所が存在することも多く、利用者の奪い合いが起きています。
このような状況では、サービス内容の違いが明確でない限り、価格競争や加算争奪戦に陥りがちです。結果として、1人当たりの単価が下がり、収益性が低下していきます。また、利用者数を安定的に確保できない事業所は、稼働率の低迷により赤字を抱えやすくなるでしょう。
デイサービスの経営改善をする方法
デイサービスの経営改善をする方法としては、以下の5つが挙げられます。
- 労働環境を整える
- ITを活用する
- 加算を算定する
- 経営戦略を見直す
- 差別化をする
それぞれの方法についてチェックしておきましょう。
労働環境を整える
デイサービスにおける職員の離職率を下げ、定着率を高めるためには、職場の労働環境を整えることが最優先課題です。具体的には、長時間労働の是正や休暇取得の促進、シフトの柔軟化、メンタルヘルスケアの導入など、職員一人ひとりが働きやすい体制の整備が求められます。
また、キャリアパスの明確化や資格取得支援制度を設けることで、職員のモチベーション向上やスキルアップにもつながります。現場の声を反映した制度設計を行うことで、職員の定着とサービスの質の両立が可能となり、結果的に経営の安定化が実現できるでしょう。
ITを活用する
業務効率化と人手不足の対策として、ITの活用は非常に有効です。介護記録や利用者管理、請求業務などは、ICTシステムを導入することで大幅に省力化できます。とくにクラウド型の介護ソフトを利用すれば、離れた場所にいる職員や管理者ともリアルタイムで情報を共有でき、ミスの削減や業務の可視化が可能です。
また、シフト作成や勤怠管理の自動化ツールを導入することで、事務負担を大きく減らすことができ、限られた人材で効率的にサービス提供を行える体制が整います。これにより、現場職員は本来業務である利用者ケアに集中できるようになり、サービス品質の向上にもつながるでしょう。
加算を算定する
介護報酬制度には、基本報酬に加えて条件を満たすことで加算を取得できる仕組みが数多く存在します。たとえば、個別機能訓練加算・入浴介助加算・サービス提供体制強化加算などが代表的で、これらを適切に取得すれば、月あたりの収益を上乗せすることが可能です。
ただし、加算の算定には人員配置や記録体制、運営方針の整備などが求められます。そのため、自施設の状況を客観的に評価し、無理のない範囲で取得可能な加算を見極めることが大切です。加算を正しく運用することで、低利益構造からの脱却を目指すことができます。
経営戦略を見直す
現在の経営方針が地域ニーズと合致しているかを再確認し、必要に応じて戦略を見直すことも重要です。たとえば、認知症専門型や短時間型のデイサービスへ移行することで、特定の利用者層に特化したサービスを提供し、差別化を図ることができます。
また、ケアマネジャーとの関係構築を強化し、紹介を受けやすい体制を整えることも収益向上に直結します。サービス内容、提供時間、送迎範囲などを柔軟に見直し、地域に根ざしたサービス展開を行うことで、利用者の満足度と稼働率を高めることが可能です。
差別化をする
競合が多いエリアでは、サービスの「差別化」が生き残るためのポイントです。他施設にはない特徴や魅力を打ち出すことができれば、選ばれる施設となる可能性が高まります。たとえば、理学療法士による本格的な機能訓練や、地域交流を取り入れたレクリエーション、季節ごとのイベント企画などが考えられるでしょう。
また、食事の質や栄養管理、清潔感のある施設環境、丁寧な家族対応など、細かな配慮が利用者やその家族からの評価に直結します。こうした見えないサービス品質を高めていくことも、大きな差別化要素となるでしょう。
デイサービスでの経費削減の手順
デイサービスでの一般的な経費削減の手順は、以下のとおりです。
- 現状の経費や収支を把握する
- 削減する経費の優先順位をつける
- 経費削減を行う
- 定期的な見直し・改善を行う
各ステップで行うことを確認し、自施設での取り組みに活かしてみてください。
現状の経費や収支を把握する
経費削減を実施するための最初のステップは、現状の支出構造と収入とのバランスを正確に把握することです。まずは月次・年次の損益計算書や現金出納帳などをもとに、人件費・光熱費・消耗品費・委託費・修繕費・車両関連費など、科目ごとに支出金額を明らかにします。
とくに、変動費(利用者数やサービス内容によって変化する費用)と固定費(家賃やリース料など定額で発生する費用)を分けて分析することで、どこに無駄があるか、どの項目が収益を圧迫しているのかを可視化することができます。このフェーズは感覚的にではなく、データに基づいて客観的に判断することが重要です。
削減する経費の優先順位をつける
次に、支出の中から削減すべきコストに優先順位をつけましょう。たとえば、食材費やレクリエーション費を削りすぎるとサービスの質が低下してしまい、利用者満足度やリピート率に悪影響を及ぼす可能性があります。
一方、見直しがしやすい経費には、電力会社や通信契約の切り替え、備品の仕入先変更、複数拠点での共同購買、無駄なサブスクリプションサービスの解約などがあります。また、外部委託している業務(清掃、送迎、給食など)がある場合、その委託費の妥当性も確認することでコスト削減につながる場合があります。
経費削減を行う
優先順位をつけた後は、実際に削減策を実行に移しましょう。この段階では、経費項目ごとに「削減目標額」「実行時期」「担当者」などを設定し、具体的なアクションプランに落とし込むことが望まれます。
たとえば、光熱費の削減であれば、省エネ機器の導入やタイマー設定の見直し、未使用スペースの電源オフの徹底など、小さな工夫の積み重ねが有効です。備品については、まとめ買いや他施設との共同購入、安価で同等の品質を持つ代替品の検討も現実的な手段です。
定期的な見直し・改善を行う
経費削減は一度実施して終わりではなく、継続的な見直しと改善が必要です。四半期ごとや半期ごとなど定期的に支出状況をチェックし、削減の効果を評価することが求められます。
また、業界の相場や他事業所の取り組み事例も参考にしながら、よりよい改善策を取り入れていく柔軟な姿勢も重要です。経費削減は、単なるコストカットではなく、「業務の効率化」「サービスの質の維持」とのバランスを取りながら行うことで、長期的な経営安定につながります。
職員からの意見募集やアイデア提案制度を導入することで、現場発の削減アイデアが集まりやすくなり、経費削減に対する組織全体の意識向上にもつながるでしょう。
まとめ
本記事では、デイサービス経営の現状や倒産件数などから、デイサービス経営の難しさを解説しました。デイサービスの経営を安定化するためには、労働環境の改善や経費削減などの取り組みが必要です。
デイサービスで経費削減を検討するなら、グローバルキッチンの介護施設向けの食事サービス「まごの手キッチン」がおすすめです。「まごの手キッチン」は、高齢者の方向けの調理済み冷凍食材をお届けする食材提供サービスです。リーズナブルで高齢者にやさしい食事を豊富に揃え、管理栄養士による毎月の献立も提供します。栄養価調整食や常食・やわらか食・ムース食にも柔軟に対応可能です。
「まごの手キッチン」の導入により、食事の用意にかかる人件費や水道光熱費など大幅なコスト削減を実現し、手間なく安全な食事を提供できるようになります。
「まごの手キッチン」では、介護施設を運営している【法人様向け】に無料試食サンプルを提供しております。ぜひこの機会に、お気軽にお問い合わせください。